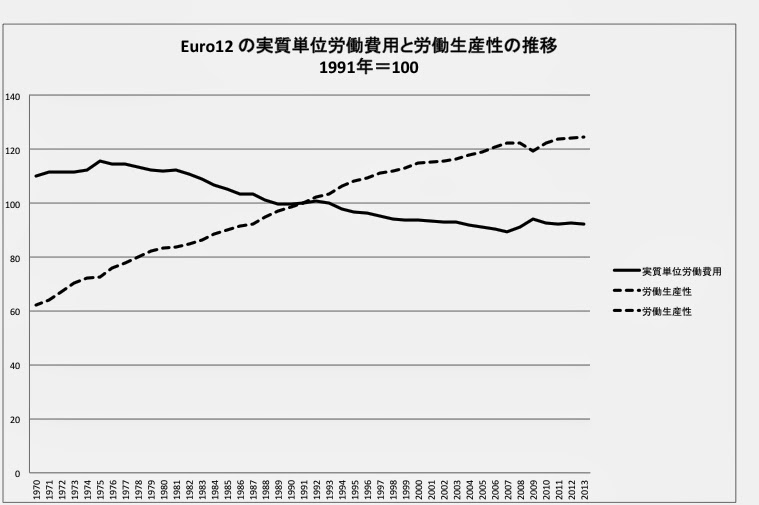フランスの家族と相続に移る前に、もう少しロシアの事情について触れておきます。
前回、ロシアの均分相続を伴う共同体家族と土地割替を伴う村落共同体について触れましたが、実は後者は19世紀から現在にいたる歴史学のきわめて大きな主題でした。
土地共有制というのは、世界的に見て決して珍しいものではありません。例えば古代中国の「均田制」やそれに倣ったとされている古代日本の「班田収受の法」は、国家の土地(公地)を公民に分与し、それに対して王朝国家が労役や生産物を徴するという制度(マックス・ヴェーバーは「ライトゥルギー」と呼び、そのような国家をライトゥルギー国家と呼びました)でした。したがって労働能力を失った人からは土地は収公されます。現代に近いところでは、近世沖縄の土地割替慣行が知られていますし、インドネシアのデサ共同体(desa)や、オスマン・トルコ治下のエジプトの土地制度がそれに類似しています。
しかし、ともかくヨーロッパ人の常識から見て、このような土地制度は奇習でした。というのも、少なくもとヨーロッパの西半分(西欧)では、封建制の時代から土地(耕地)は農民の私有地(Hufe、virgate、mansusなど)だったからです。
ロシアの共産主義的土地制度は、一般的にはハクストハウゼン(August von Haxthausen)の『ロシア研究』(1848)によって知られてから、その起源が西欧における知的興味の対象となりました。ちなみに、ハクストハウゼンは、その「太古的(uralt)起源」について語りましたが、決して実証研究をしたわけではありません。すでに19世紀中頃には先駆的な研究書が現れますが、本格的な実証的歴史研究は19世紀末から始まったといってよいでしょう。研究は20世紀に入り密度を増し、ソ連時代にも続けられました。
その結果、現在までに多くのことがはっきりとしています。
まずどのように古くさかのぼっても16世紀以前には、土地割替を伴う土地共有制は存在しなかったことがわかっています。つまりそれは起源的にはきわめて新しいものです。
そのことは16世紀頃のロシアの農村事情を知れば、自ずと理解されます。
当時、ロシア(1917年以前の用語法では大ロシア)では、農民(村落住民、krest'iane)は、セロー(selo)と呼ばれる村落か、ジェレーヴニャ(derevnia)と呼ばれる小部落に居住していました。ここでは仮に前者を村、後者を部落と訳しておきますが、それらのほとんどは1世帯または2、3世帯からなる集落であり、多少とも大きな集落をイメージするのは誤っています。むしろ散居制に近い状態でした。
ところで、その頃の状態を示した史料には、「村と諸部落」(selo s dervniami)という表現が繰り返されていますが、もちろん、この表現は村落間に何らかの結びつきがあったことを示しています。端的に言うと、普通、村にはキリスト教(正教会)の教会があり、周辺の諸部落から日曜日に信徒(農民)たちが参集していました。つまり、村と諸部落というのは教区でした。
ロシアの多くの歴史家は、いくつかの史実を根拠にして、この「村と諸部落」が同時に広域的な行政団体であり、かつ土地共同体(郷、volost')を構成していたと考えています。ただし、土地割替が行われていたというわけではありません。むしろ、逆です。この点について、ソ連の多くの研究者は、帝政末期の歴史家、クーリッシャー(Iosif Kulisher)の研究(『ロシア経済史』)に従っているように思います。
そもそも16世紀の時点では、広大な領域内に多数の部落が存在していたとはいえ、土地に比して人口は圧倒的に少数でした。開墾されていない「自由な土地」(広大な森林)が広がっていました。このような状態のもとで、郷の領域内では部落、つまり農民世帯(またはその少数の集合)による土地の「自由占取」(freie Okkupation)が行われていたと考えられます。当時の史料に頻繁に出現する「鋤、鍬、鎌のゆくところ」(自由に占取できる)という表現がそのことを示します。またいったん開墾された土地がしばしば放棄されて荒廃地(pustosh)に変じていたという事情もそのことを支持します。
しかし、変化は徐々に、しかし確実に生じてきました。一つの顕著な変化は、郷内の人口と世帯数が16世紀から18世紀にかけて急速に増加したことです。すでに17世紀から18世紀に、村や部落がかなり多数の農家世帯を数えるほどに大規模化していたことが分かります。そして、それとともに注目されるのが、各郷内の部落間において土地紛争が発生しはじめていたことです。部落(農民世帯の近所)から始まった森林開墾(自由占取)の動きは次第に部落の周辺部に向かい、そこで部落と部落との土地をめぐる接触と紛争がはじまったと考えられます。このことは自由占取の時代が終わったことを意味していました。
あらためて言うまでもありませんが、新たに開墾する土地がなくなったとき、村落内の人口増加に対処するためには、すでに開墾した土地を住民間で再配分するしか方法はありません。そして、史料はまさにこの頃に土地割替が始まったことを明示しています。
1861年の農奴解放令では、こうして土地を共有し、ときおり割替を行う団体(村、部落またはそれらの連合体)は、「共同体」「村団」(obshchestvo、obshchina)の名称を与えられ、正式に「農民法」の一部として承認されるに至ります。
ただし、ここで注意しなければなりませんが、自由占取の時期が終われば、自動的に土地割替を伴う土地共有制度に移行するというわけではありません。実際、西欧の多くの地域では、11世紀〜13世紀の森林開墾の終了時にフーフェ制(形式的平等原則にもとづく私有制)に移行し、それにもとづく村と土地制度の再編成を行っています。しかも、こうした変化の波は、ロシアの西側、または西欧の東側に位置するポーランドやリトアニアでは16世紀〜17世紀に及んでいます。
一体、ロシアでは如何なる事情が土地割替を伴う土地共有制度をもたらしたのでしょうか? これはかなり難しい問題であり、簡単に答えのでる問題ではありません。少なくとも、次のような点を合わせ考えないとならないでしょう。
1 それまでの農民世帯・家族のありかた(農家の家族形態や相続戦略)
16世紀以前の状態はよく知られていませんが、少なくとも近代にはロシアは男子間の均分相続制度を伴う典型的な共同体家族の国になりました。
2 政治的条件(イワン雷帝からピョートル大帝にいたる政治史)
ロシアの専制国家化(家産官僚制国家の成立)と、ロシア国家・ツァーリ=皇帝の対農村租税政策などの作用が分析されなければならないでしょう。特に農民階層に重くのしかかった人頭税の作用が考慮されなければなりません。
また西欧の多くの国・地域と異なって、ロシアでは、16世紀以前の旧分領制時代の支配階層だった公とボヤールは、半ば強制的に半ば自発的に実施していた均分相続制の下で零細化し、没落しました。それに代わって16世紀以降に登場してきたのが、公とボヤールの家臣からツァーリの家産官僚に転じ、国家から秩録として一代限りで土地を与えられた宮廷貴族(ドヴォリャーニン)でした。彼らは少なくとも出発点においては、ツァーリ=皇帝の徴税請負人の役割を演じました。(その退廃的な姿は、ゴーゴリの小説『死せる魂』の中に見ることができます。)
3 ロシア正教の作用
(これについては、機会をみつけて論じます。)
最後に一言。
ロシアでは、以上に示したような土地制度の中で、各農家に対して概ね男性人口(納税人口)を基準として「平等に」耕地が配分されたため、また当然ながら土地配分時の各農家の男性人口が異なっていたために、農家に配分され・耕作される土地面積がバラバラになりました。土地台帳から見ると、農家の男性人口は零から10人を超えるものまで様々でした。
これは、一見して、どのような時点でも農民階層の両極への分解が生じているかのような外見を呈する理由になりました。
しかし、ロシアの経済学者(例えばA・チャヤーノフ)は、この点でも大きな仕事をしました。つまり、ある時点(例えば1900年)に大家族であり経営面積も広い農家が10年後(1910年)には家族分割(財産分割)によってより小さな経営に移行しており、逆に最初に小経営だった家族が後により大きな経営に移行するということが見られました。(この点でトゥーラ県の統計はきわめて貴重な統計的貢献を行いました。)
ともあれ、こうしてロシアでは1930年頃まで、共同体的土地所有と均分相続制度の下で農村人口・農業人口が急速に増加してゆく、という西欧諸国ではあまり見られなかったような事態を経験することになりました。しかも、ロシアの西側に隣接するほとんどの諸国が工業化と都市化を達成し、経済発展を遂げているときにです。
ある意味ではスターリンの経済政策をそれに終止符を打とうとするものであったということができます。
賃金主導型の成長
これこそ私が主張している戦略に他なりません。
しかも、それは現在世界の多くの優れた研究者によって主張されています。
以下は、現在世界で最も注目されている経済学者(Marc Lavoie とEngelbert Stockhammaer 氏の編著、ILO)の出版した本の紹介の紹介です。
Marc Lavoie to Engelbert Stockhammer 氏は、これまで精力的に研究を公表してきましたが、それをまとめたものです。
Marc Lavoie to Engelbert Stockhammer 氏は、これまで精力的に研究を公表してきましたが、それをまとめたものです。
「本書は、資本(大企業)を優遇する分配への移行と所得不平等の拡大が経済成長を抑制し、経済的な不安定性を増したことを主張しています。それは賃金の抑制のリスクが現実のものとなっており、また負債主導型(欧米日のバブル型のこと)および輸出主導型の戦術(日本やドイツを始めとして)が多くの国で追求されているが、これらの経済問題と結びついていることを示しています。
一方、本書は、賃金主導型の復興のための政策インプリケーションと戦術を分析し、賃金主導型の復興が、消費支出を維持するために必要な家計債務の拡大と、また賃金抑制に基礎を置く新重商主義的政策と結びついたグローバルな問題を軽減することを示しています。その発見は、機能的な所得分配の「バランスを回復する」必要を示しています。賃金を優遇したこの「バランスの回復」は公正で持続可能な成長の本質的な要素であり、強固な政策調整を求めます。賃金主導型成長は、現在および将来の研究者ならびに政策担当者にとって有益な共通の枠組みを提供しています。
Palgrabe Macmillan社との共同出版であり、労働研究における進展シリーズの一部です。
目次
序論
1 賃金主導型成長:概念、理論および政策
2 賃金シェアーの低下の原因。機能的所得分配における決定要因の分析
3 総需要は賃金主導的か利潤主導的か? グローバルモデル。
4 賃金主導型または利潤主導型供給。賃金、生産性および投資
5 大不況とグローバル不均衡の原因としての所得不平等の役割
6 金融化、金融・経済危機、および賃金主導型復興のための要件と潜在的可能性」